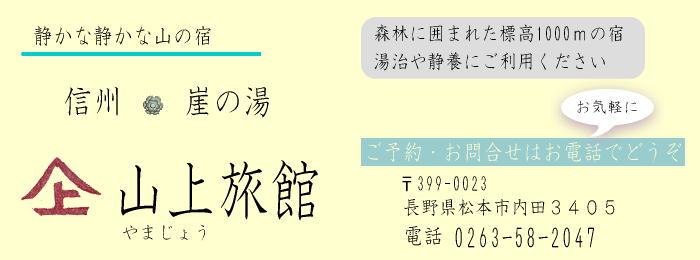 |
|
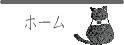 |
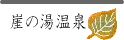 |
 |
 |
 |
崖
の
湯
温
泉 |
 泉質 泉質 |
カルシウム・マグネシウムー硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉
(低張性中性冷鉱泉)
|
 適応症等 適応症等 |
(一般的適応症)
筋肉もしくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経症、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
(泉質別適応症)
きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症
(飲用泉質別適応症)
胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風)
(禁忌症)
病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
|
 |
| |
 沿革 沿革 |
鎌倉時代、当地方の豪族だった八軒長者が館を築き付近を治めており、塩ノ池を作り、館の用水としていましたが、長雨により、この池が決壊してしまいました。この決壊によって地底より霊泉が湧出するようになり、傷ついた猿がこの霊泉にて治療していたと言い伝えられております。
明治7年、百瀬彦太郎がこの地を湯治場として開発。傷、リウマチ、神経痛に卓効があることがわかりました。
隣接する薬師堂には、歩くことが困難だったお客様が湯治によって治り、杖もいらなくなり、願果した杖を修められて、お帰りになっております。 |
 |
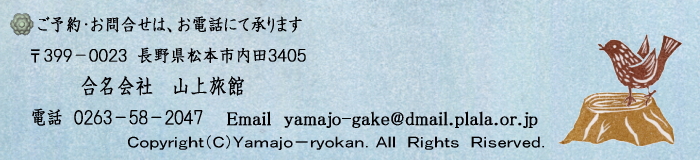 |